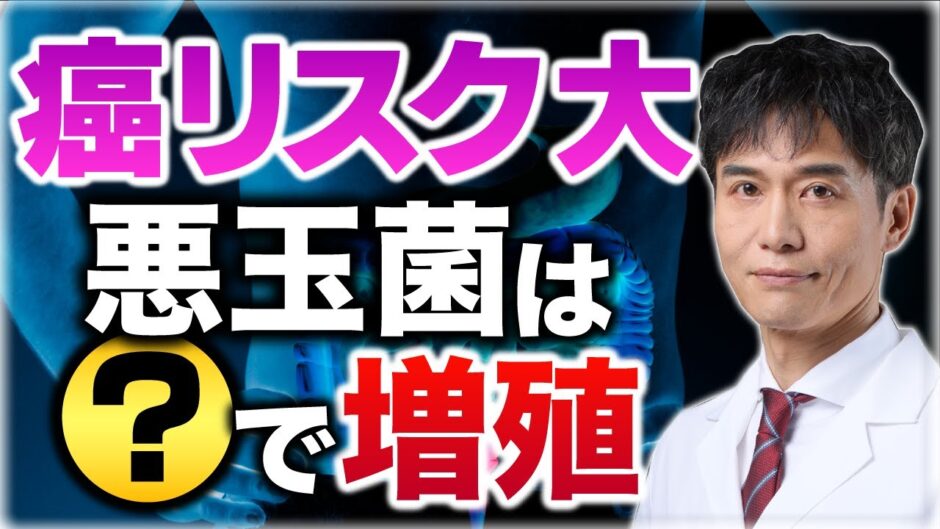石黒です。

がん予防における腸活の重要性についてお話ししたいと思います。
なぜ腸活をするとがんを予防できるのか?と、摂ってはいけない食品や、摂るべき食品についてもお伝えしますね。
あなたの普段の生活が腸内細菌にとって、良いことをしているかどうかをチェックしながら読んでみてください。
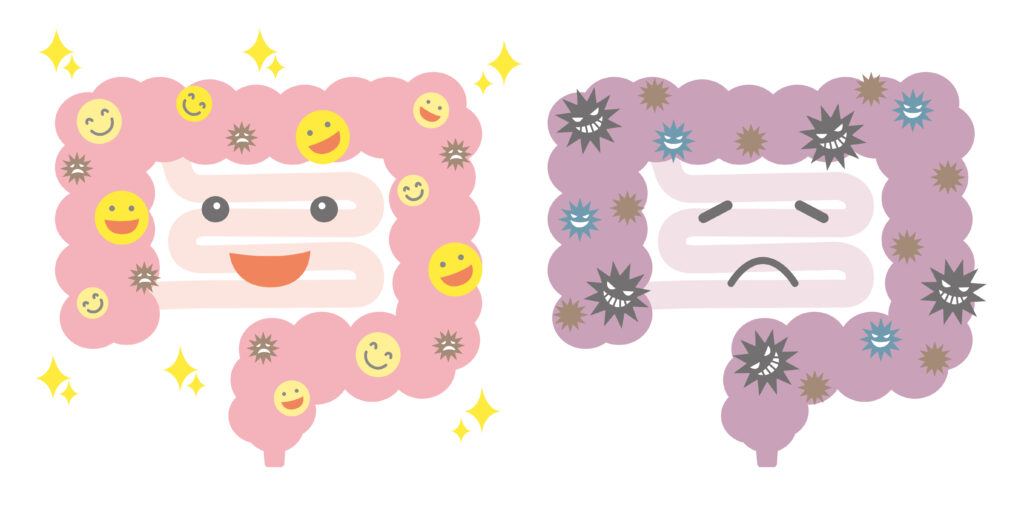
腸内細菌とがんの密接な関係性
実は、腸内細菌とがんとの間には密接な関係があることが近年の研究で明らかになっています。腸内細菌の構成は、病気の発生や予防に大きな影響を与えるとされ、腸内の環境が心臓や肝臓、脳、皮膚、肺など多岐にわたる臓器の機能に良い影響を及ぼします。
特にがんとの関連では、腸内細菌が免疫機能に影響を与え、肝臓がんのリスクが高まることがあります。また、抗生物質の使用は腸内細菌の組成を大きく変えることがあり、これが免疫システムに重大な影響を及ぼすことがあります。
腸は免疫システムの中心であり、腸内細菌は人の免疫力に大きく影響します。腸内細菌のバランスの乱れは、肥満やうつ病、パーキンソン病、アレルギー性疾患など、多くの病気の原因になります。がんについても、腸内細菌が重要な役割を果たしていることがわかっています。
これまでの研究で、特定の腸内細菌は腸の炎症を抑えることで体全体の炎症を減らす効果があることがわかっています。しかし、逆に別の菌種はただ存在するだけで炎症を促進し、腸の保護層を破壊し、がんを引き起こしやすい環境を作ってしまうことも示されています。

腸内細菌の良し悪しが病気の治療効果にも影響
この認識は、腸内細菌が免疫に直接影響を及ぼすことが臨床現場でも認識されており、がん治療後に行われる抗がん剤治療や免疫療法で、腸内細菌の良し悪しが治療効果に大きく影響することが知られています。ですから、良好な腸内細菌をどのようにして維持するかが、がん治療の成功にとっても非常に重要であるという認識が広がりつつあります。
腸は、僕たちがよく「第二の脳」と呼んでいるほど、実は神経組織であり、非常に重要な役割を持っています。通常、神経組織と言えば、脳や脊髄のような中枢神経系が思い浮かびますが、腸内にも腸管神経系と呼ばれる神経のネットワークが存在します。精子と卵子が受精してできた受精卵から組織が発達する過程で、神経組織の原点が分かれ、一部は脳を形成し、もう一部は腸の神経になります。つまり、脳と腸の神経系は元を同じくしており、生まれた後もこの二つを繋ぎ続けるのが迷走神経です。このことからも、腸の健康が全身の健康にどれほど影響を及ぼすかがわかります。
腸は第2の脳。脳は腸内関係の影響を受けやすい
迷走神経は、脳と腸を直接つなぐ太い神経で、腸内細菌から脳への情報伝達の主要な経路であることが分かっています。このことから、迷走神経の役割は非常に重要だと理解されています。
実際に、迷走神経の機能を向上させるのが腸内細菌であることもわかっています。がんの発症においてストレスが大きな役割を果たしており、ストレスへの反応は腸内細菌によって大きく左右されます。腸内環境が整っていると、ストレスが同じであっても、免疫機能の低下を防ぎ、より健康を維持できるとされています。

腸内関係を整える3つ方法
普段から腸内環境を整えるために、気をつけてほしいことが3つあります。
まず一つ目は、砂糖の摂取を減らすことです。砂糖は、体にとってあまり良くない影響を与え、特に腸内の悪玉菌が好むため、できるだけ摂取を控えめにしましょう。特に、加工食品に含まれる砂糖を避けることが大切です。
二つ目は、食物繊維をしっかりとることです。善玉菌は食物繊維をエサとしていますので、野菜や果物など、食物繊維が豊富な食品を積極的に摂取することが、腸の健康につながります。
そして三つ目は、日本の伝統的な発酵食品を定期的に取ることです。納豆やぬか漬けなどの発酵食品には、腸内環境を良くする効果があるので、これらを日々の食事に取り入れて、腸の健康を保ちましょう。
あとは、抗生物質の使用を減らすことが大事ですね。ちょっとした風邪で医者に行き、抗生物質を飲むより、早めに休んで自然に治すことが大切です。抗生物質は、本当に必要な時以外は避けるべきですが、僕たちが知らず知らずのうちに摂取してしまうこともあります。特に、工業的に育てられた牛や豚、養殖された魚などは、病気予防のために抗生物質を投与されていることが多く、そのような食品から抗生物質を摂取してしまうことがあります。

そういった食品の摂取頻度を減らすことも、抗生物質摂取を控える上で重要です。また、野菜や果物からも少なからず抗生物質を摂取している可能性がありますが、できるだけリスクを減らす努力をしましょう。抗菌作用のある塩素を含んだ水道水を直接飲むことも避け、浄水した水を飲むようにするなど、日常生活でできる工夫が大切です。
このように、日々の生活の中で腸内細菌を健康に保つための工夫をすることが、将来のがん発症リスクを減らすことに繋がります。食生活を見直して、がん予防に役立つ食事法を取り入れてみるのも良いでしょう。僕の本には、がんを予防するためのレシピも紹介していますので、興味があればぜひ一度手に取ってみてください。 ⇒僕の本はこちら
※この記事は、下記の動画を要約したものです。
詳しく知りたい方は、下記の動画をご覧ください。
合わせて他の記事や動画もご覧ください。(本ページの下部からご覧になれます。)
よければYoutubeでのみんなのコメントも参考にしてみてくださいね。(動画の左上のタイトルを押すとYoutubeに飛びます。)